はじめに
最近、「米国株が割高」「バフェットが株を売っている」「AIバブルでは?」といった話題をよく耳にするようになりました。
確かに、PERやバフェット指数(Buffett Indicator)などを見ると、過去と比べても高水準にあります。
しかし、割高=すぐ暴落というわけではありません。今回は、こうした「過熱サイン」を冷静に整理し、私たち個人投資家がどう向き合うべきかを考えます。
米国株は本当に割高なのか?
🔹 バフェット指数が過去最高水準に
バフェット指数とは「株式市場全体の時価総額 ÷ 名目GDP」で算出される指標です。
2025年現在、この数値はおよそ217%と過去最高クラス。
ITバブル(2000年)やコロナ後の高値(2021年)を上回る水準で、「火遊びゾーン」とも呼ばれています。
🧠 ポイント
- 一般的に120〜150%が「やや割高」ライン
- 200%を超えると「過熱」と判断される傾向
ただし、現代の米国企業は海外での売上比率が高いため、「GDPだけで割高とは言い切れない」という指摘もあります。
🔹 PERも高水準、利益成長に追いつけるか
S&P500の予想PER(株価収益率)は約30倍前後。
これは、ITバブル期や2021年の超金融緩和期と同レベルです。
つまり、市場はすでに「AI関連の成長期待」を織り込んでおり、実際の利益がそれに追いつけるかどうかが焦点になっています。
バフェットが株を売っている理由とは?
世界的投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、ここ12四半期連続で「株の売却超過」を続けています。
2025年9月期には、約125億ドルを売却、買いは約64億ドルと報じられました。
現金比率はおよそ30%に達し、慎重な姿勢を見せています。
ただし、これは「暴落を予想している」というよりも、
「次の投資チャンスを待つ準備」と見る専門家も多いです。
「高値圏で焦って買わず、待つ勇気を持て」というのが、バフェット流の鉄則
AIブームは“新しいバブル”なのか?
AI関連企業、特にNVIDIAなどの半導体株に資金が集中しています。
AI投資が企業の生産性を押し上げている一方で、「期待先行すぎる」という声も。
過去のITバブル時(2000年)と同じように、“成長物語”が株価を押し上げている構図に似ています。
ただし今回は、AIが実際に収益化段階へ進んでいるため、単なるバブルと断定するのは早計かもしれません。
割高相場との向き合い方
💡 割高=売りではなく、慎重な買い時期
市場が高値圏にあるときは、焦って「全部売る」よりも、
新規投資を少し控えて様子を見ることが有効です。
すでに長期で積み立てている資産(オルカン、NASDAQ100など)は、
方針を変えずにコツコツ継続でOKです。
💡 現金・安全資産を厚めに
割高局面では、「現金」「ゴールドETF」「債券ETF」など、
リスク分散のための資産を厚めに持つのも有効です。
次の下落時に備えて現金ポジションを確保しておくことで、
「買いたいときに買えない」リスクを避けられます。
💡 テーマ株は少なめ、分散重視で
AIやテクノロジー関連など、一部のテーマ株に集中してしまうと、
調整局面で大きく下げるリスクがあります。
主力は全世界株・S&P500などの分散型、テーマ株はあくまで“スパイス”程度に。
ことり流まとめ
- バフェット指数やPERの高さは“過熱注意”のサイン
- バフェットが売っているのは、チャンスを待つための現金化
- 割高=暴落確定ではなく、冷静な分散と待機がカギ
- 現金・ゴールドなどリスク分散を意識
- 長期投資はブレずに継続、短期テーマ株は慎重に
おわりに
「米国株は割高」と言われても、それだけで投資を止める必要はありません。
大切なのは、市場の熱を冷静に見極め、自分の資産配分を保つこと。
焦らず、バフェットのように次のチャンスを待つ余裕を持ちたいですね。
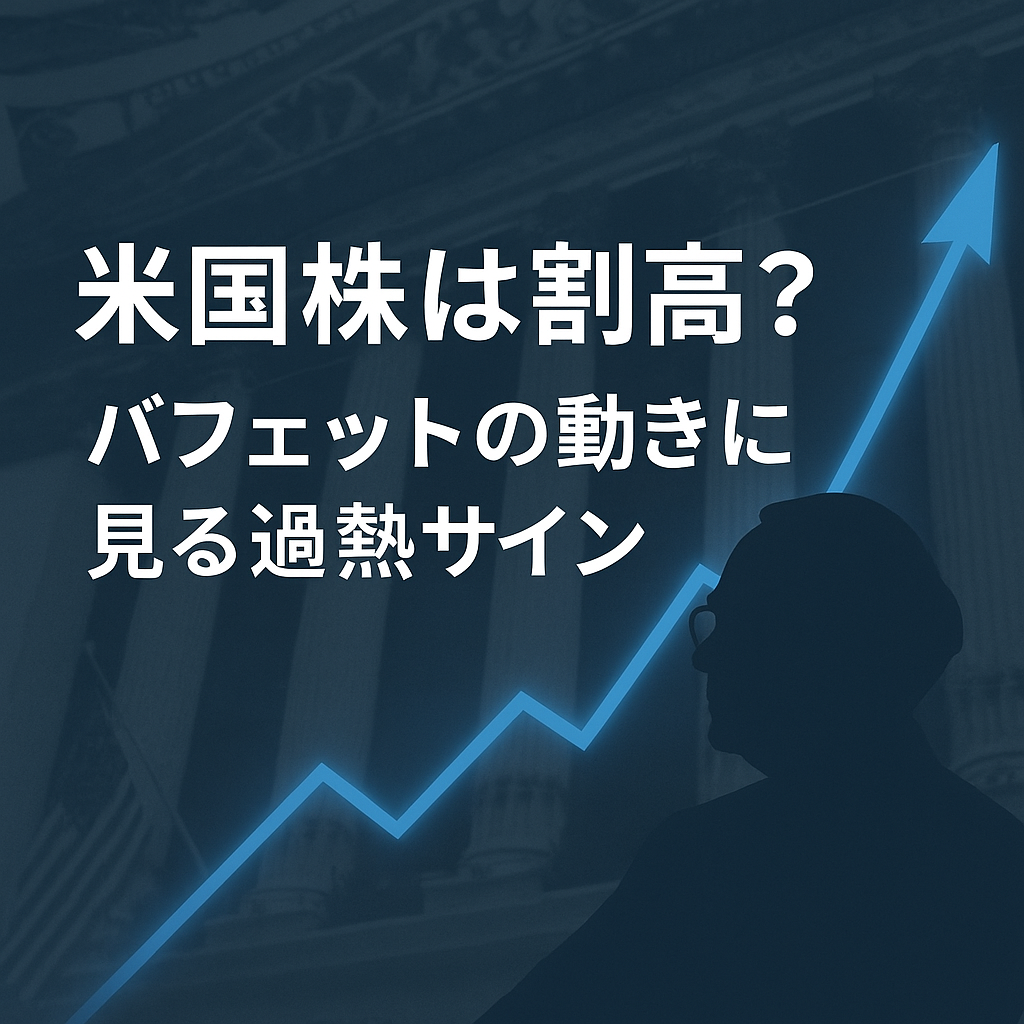
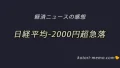

コメント