金融所得課税とは?なぜ注目されているのか
金融所得課税とは、株や投資信託の売却益、配当金、利子などの**「金融から得る利益」に課される税金のことです。
現在は一律で20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別税0.315%)が課されています。
この税率は給与などの「総合課税」と比べて低く、
「高所得者ほど有利では?」という指摘が以前からありました。
そのため、政治の世界では定期的に**「格差是正」や「再分配」**の観点から見直し議論が浮上します。
高市総理で再び浮上する「増税案」
新政権が誕生し、高市総理のもとで再び注目されているのが金融所得課税の見直しです。
高市氏はもともと「財政健全化」と「社会保障の安定財源の確保」を重視するタイプで、
増税を“否定しない現実派”として知られています。
背景には、
- ガソリン減税の穴埋め(約1.5兆円)
- 年収の壁対策による財源不足(約1.7兆円)
といった要因もあり、**「金融所得課税を代替財源に」**という見方が一部で広がっています。
金融所得課税の税収はどのくらい?増税したらどうなる?
国税庁の統計などをもとにすると、
課税対象となる金融所得の総額は年間およそ50兆円前後と推定されています。
(この金額にはNISAなどの非課税分は含まれていません)
この金額に現在の税率20.315%をかけると、単純計算で
約10兆円(=50兆円×0.20315) の税収規模になります。
ただし、実際には
- 損益通算や繰越控除
- 少額の未申告取引や控除対象
などがあるため、国庫に入る実際の税収はその半分程度。
そのため、実際の税収は3〜5兆円前後と見られています。
税率が30%になった場合の影響
仮に税率が20%から30%に引き上げられた場合、
単純計算で税収は1.5倍になります。
- 現行:3〜5兆円
- 30%の場合:4.5〜7.5兆円
これは政府が探している「数兆円単位の財源確保」にピッタリ当てはまる規模です。
ガソリン減税や社会保障費をまかなう“現実的な選択肢”として、
金融所得課税が検討されるのも自然な流れといえます。
金融所得課税が株式市場に与える影響
金融所得課税の引き上げは、投資家心理や市場全体に複雑な影響を与えます。
🏦 投資マインドへの影響
税率が上がれば手取りリターンが減少します。
個人投資家にとっては「売っても税金が増える」「配当も減る」といったマイナス材料になり、
短期的には「利益確定売り」や「様子見ムード」が強まる可能性があります。
ただし、実際の政策決定が長期化する場合は、
一時的な調整にとどまるケースも多いです。
🌏 海外への資金流出リスク
富裕層ほど税制変更の影響を受けやすく、
税率引き上げが続けばシンガポールや香港など税率の低い国への資金移動が加速する可能性もあります。
これを防ぐために政府はNISAなどの非課税制度をさらに拡充する可能性があります。
📊 市場全体への影響は限定的?
日本株全体では、海外投資家の売買比率が高いため、
税制変更が即座に株価全体を押し下げるとは限りません。
ただし、中長期的には「高配当株ブームの一服」や「国内マネーのリスク回避傾向」など、
投資行動の変化を招く可能性があります。
将来的な「段階的増税」への懸念
政府が金融所得課税を見直す場合、いきなりではなく段階的な制度設計になるとみられています。
しかし、一度“課税の見直し”が始まると、
将来的にさらなる税率引き上げや課税対象の拡大へ進むリスクもあります。
過去の消費税やたばこ税のように、「一時的」「限定的」と言われた増税が
最終的に恒久化した例は少なくありません。
投資文化を根づかせるためにも、
投資への過度な課税強化には慎重であるべきだと感じます。
国民の資産形成を支える政策と、財源確保のバランス。
この2つをどう両立させるかが、今後の焦点になりそうです。
金融所得課税以外の代替案は?
金融所得課税だけに頼らず、公平性・成長・財源確保を両立できる方法もいくつか考えられます。
ここでは現実的な5つの代替案を紹介します。
① 高所得層への総合課税の段階的強化
年収1億円以上などの高所得層に限定して、金融所得を総合課税化する方法。
「一律増税」ではなく“ピンポイント課税”にすることで、中間層への影響を抑えられます。
② 法人税の優遇見直し
大企業に適用されている研究開発減税などの税優遇を部分的に縮小。
個人投資家への影響を避けつつ、財源を確保できる現実的な手段です。
③ 富裕層向けの相続税・贈与税の見直し(国際比較を踏まえて)
相続税は「資産を次世代へ受け継ぐときに課される税金」ですが、
その仕組みや税率は国によって大きく異なります。
🌏 各国の実情
| 国・地域 | 制度の有無 | 税率の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | あり | 最大55% | 世界でもトップクラスの高さ。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」。 |
| 🇺🇸 アメリカ | あり(連邦+州) | 最大40% | 約13億円(850万ドル)まで非課税。富裕層のみ対象。 |
| 🇬🇧 イギリス | あり | 一律40% | 約5,000万円まで非課税。夫婦間は全額免除。 |
| 🇫🇷 フランス | あり | 最大45% | 親子間で17〜45%。 |
| 🇩🇪 ドイツ | あり | 最大30% | 親子間は最大30%、兄弟姉妹は最大50%。 |
| 🇰🇷 韓国 | あり | 最大50% | 日本に次ぐ高水準。サムスンの相続で話題に。 |
| 🇸🇬 シンガポール | なし | – | 2008年に廃止。富裕層誘致政策の一環。 |
| 🇭🇰 香港 | なし | – | 2006年に廃止。アジア資本を呼び込む目的。 |
| 🇨🇦 カナダ | なし(譲渡益課税型) | – | 相続時に資産を「売却した」とみなし課税。 |
| 🇦🇺 オーストラリア | なし | – | 1979年に廃止。 |
💬 解説
日本は、税率が高く・控除が少ないことが特徴です。
基礎控除が低いため、都市部では中間層でも課税対象になるケースが増えています。
「相続税を払うために家を売る」という話が出てくるのは、この構造が原因です。
一方、アメリカやイギリスのように「富裕層のみを対象にする国」や、
シンガポール・香港のように「相続税そのものを廃止して資産流入を促す国」もあります。
ことりの考え
せっかく築いた資産を次の世代に残そうとしても、
そのたびに重い課税がかかるのは努力の成果を引き継げない不公平感を生みやすいと思います。
相続税そのものを廃止するのは現実的ではないとしても、
- 基礎控除の引き上げ(中間層を課税対象から外す)
- 段階的な緩和や軽減措置(住宅・事業承継への配慮)
といった、より公正で現実的な制度に見直すことが大切だと思います。
本来の目的は「格差是正」であり、中間層から取りすぎる税ではないはずです。
日本も他国のように、“富裕層限定型”の仕組みへ修正していくべきでしょう。
④ 消費税の一時的調整+給付金併用
近年、物価高や可処分所得の減少を背景に、国民の間では「消費税減税」を求める声が強まっています。
実際、食品や生活必需品の税率を引き下げる「軽減税率の拡大」や、
一時的な消費税率1〜2%の引き下げを求める動きも見られます。
💬 代替案:
- 消費税を一時的に0.5〜1%引き下げ
- 同時に、低所得者層への**給付金(定額支援やポイント還元)**を実施
- 減税による税収減を、他の歳出見直しや一時的な赤字国債で補う
この方法は、国民の負担感を直接和らげつつ、景気下支え効果も期待できる点で政治的にも支持されやすい案です。
ただし、財政の持続性を考えると、恒久的な減税ではなく、
期間限定・対象限定の「一時的措置」として実施することが現実的といえます。
⑤ 歳出の見直し(無駄削減)
増税だけでなく、支出の優先順位づけも重要。
補助金や一時的な事業を削減し、教育・研究など“未来への投資”に重点を置くことが求められます。
ことりの見解
私は、投資文化を壊すような一律増税よりも、
「高所得層・法人・相続」など、よりバランスの取れた負担の分配を進めるべきだと思います。
金融所得課税を強化すれば一時的な税収は増えますが、
投資マインドの冷え込みや、国内資金の流出リスクを招くおそれがあります。
政府が本気で“貯蓄から投資へ”を進めたいなら、
非課税制度の拡充と公平な税負担を両立させること。
単純な「増税」ではなく、賢い再分配の仕組みが必要です。
投資家ができる備え
- NISAの非課税枠を最大限活用する
- 高配当よりも成長株・再投資重視の戦略へ
- ゴールドや海外ETFなどへの分散投資
税制変更に一喜一憂せず、長期・分散・非課税運用を軸にすることが、
これからの時代の“防御策”になるでしょう。
📘 まとめ
・金融所得課税は年間3〜5兆円規模の税収
・30%へ引き上げられると4.5〜7.5兆円規模に拡大
・一度始まると段階的増税のリスクも
・代替財源は「高所得層・法人・相続課税」が現実的
・投資家はNISA・分散運用で備えるべき
もし内容に誤りや気になる点がありましたら、ぜひコメントで教えてください。皆さまのご指摘やご意見が、記事の品質向上につながりますので大変ありがたいです。
この記事が参考になったら、ぜひ下のバナーをポチッと応援してもらえると嬉しいです!
(ランキングが上がると更新の励みになります🌷)
関連記事
給料に税金、投資にも税金?知らないと損する“二重課税”の仕組み

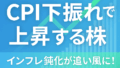

コメント
NISAがあるから増税してもいいという意見もありますが、それこそ政府の思惑通りです。NISAはいったん売れば次買えるまで1年かかります。これは個人投資家に株の底ざさえをさせているのと同じです。しかも、損した分は損益通算できません。税率が30%になった場合も所得50万以上ならとか高市さんはいかにも緩和的なことを言っていますが、どうやって源泉徴収の段階で総所得を把握するんでしょうか。証券会社同士が連携して個人の源泉徴収の状況を送りあうんでしょうか。これこそ政府による資産把握です。そして、資産把握されたのち源泉徴収の実質総合課税化、社会保険料徴収へと進むのは確実です。そうなれば源泉徴収ですましている人は来年社会保険料が増額されていて驚くことになります。しかも、来ないとどれだけ上がったかは把握できないでしょう。政府は我々よりもっとシビアに歳入、歳出のシミュレーションをしているはずです。そして、そのための制度を徐々に国民を懐柔しながら達成していきます。結局物価高対策と言いながら将来的な増税についての施策ばかりしているということです。
通りすがりさん、詳細なご意見ありがとうございます。
ご指摘のように、NISA制度は非課税の恩恵がある一方で、売却後の再投資までのタイムラグや損益通算の制限など、制度設計上の制約も存在します。
また、金融所得課税の再構築が進む中で、マイナンバーを通じた資産情報の一元管理や、将来的な社会保険料算定への連携といった議論も確かに注目されています。
政府の財政再建方針と個人資産課税の方向性がどのように整合されていくのか、今後も注視していく必要がありそうです。
建設的なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
ttps://mainichi.jp/articles/20251112/k00/00m/010/274000c
非常に厳しいニュースになります。
一体政府は何を考えてるんでしょうか。
高市政権は国民不在の暴走政権に思えます。
ここまで保険制度が崩壊しているのでしょうか。